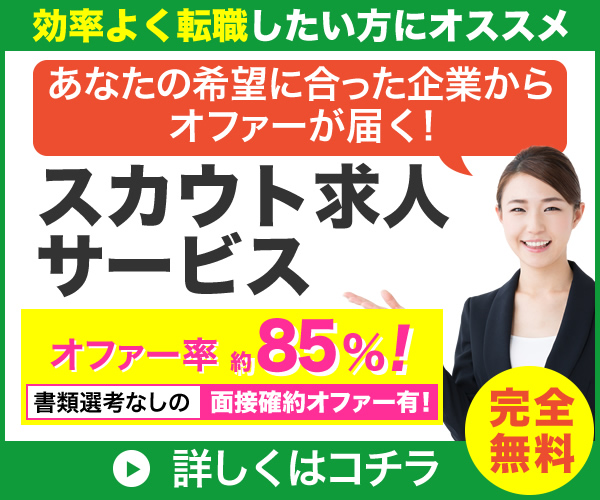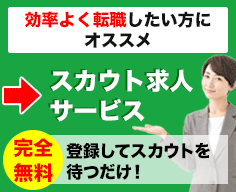人材育成でシニア社員の活性化を図る方法とは
<PR>転職のプロによる充実のサポートで転職成功を目指す!うれしい遠隔サポートも◎
サポートを受けながら転職活動を成功させたいあなたにオススメなのが、【転職支援実績No.1(※1)】の『リクルートエージェント』です。
公開求人は約11万件、非公開求人は約15万件(※2)。経験豊かなキャリアアドバイザーが、あなたの希望やスキルに合う求人を紹介してくれます。
書類添削、面接対策、面談調整、条件交渉なども代行してくれるため、転職が初めての方や忙しい方にもぴったり。転職のプロから充実したサポートを受けたいなら、今すぐ登録を!
(※1)厚生労働省「人材サービス総合サイト」における無期雇用および4ヵ月以上の有期雇用の合計人数(2019年度実績)2020年6月時点
(※2)2021年3月31日時点
労働力不足の今、企業にとってシニア世代は貴重な戦力となるでしょう。
定年が延長されるといった法改正が行われるなど、今後はシニア世代の社員を活性化させることが重要になります。
今回はシニア世代の人材育成の課題やメリットなどを解説します。
40代50代におすすめの転職サービス
40代50代におすすめの転職サービスを紹介します。
サービスによって求人の内容が異なりますので、様々な転職サービスに登録することをおすすめします。
良い求人が見つからなかった、紹介されなかった場合はすぐに退会しても問題ありません。
| 転職サービス | こんな方に おすすめ | 特徴 |
|---|---|---|
|
レバテックキャリア |
40代のITエンジニア経験者 |
|

リクルートエージェント |
転職を考えているすべての方、正社員希望の方 |
|
|
リッチマン介護 |
介護職を希望の方 |
|
シニア社員を取り巻く現状

少子高齢化など時代や環境が変化し、シニア世代の社員を取り巻く環境も変わりつつあります。
まずは、どのような変化があったのか、その現状を見ていきましょう。
◆「70歳までの就労機会確保の努力義務」とは
2021年4月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、「70歳までの就労機会確保の努力義務」が新たに課せられました。
厚生労働省の「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」によると、具体的には、事業主に下記のような措置を求められています。
(1)70 歳までの 定年の引上げ
(2)定年制 の廃止
(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
この改正は個々の特性や希望を踏まえて、70歳までの就業機会を確保するためのもので、定年年齢を70歳に引き上げるものではありません。
◆「70歳までの就労機会確保の努力義務」への対応状況
パーソル総合研究所「企業のシニア人材マネジメントに関する実態調査(2020)」によると、企業の対応として最も多いのは、「定年後再雇用制度」となっています。
「すでに実施中」「検討中」を合わせて86.1%の企業が選択肢として検討しているという結果です。
その他の対応としては、「正社員としての定年延長」や「他企業への再就職支援」、「フリーランスとして就労するためのサポート」などがあります。
◆定年再雇用者の年収と職務の変化
実際に定年後再雇用制度を適用したシニア社員の働き方を見ていきましょう。
まず年収の変化を見てみると、再雇用前と比べて平均で44.3%低下したという結果が出ています。
再雇用者の55%は「定年前とほぼ同様の職務」という結果も出ており、職務内容に関わらず、定年後の再雇用では年収が下がるのが現状です。
仕事内容は変わっていないのに収入を低くされれば、以前と同じようなモチベーションを保つことが難しくなり、パフォーマンスにも影響が出るでしょう。
◆シニア社員は企業の期待に応えているか
では、シニア社員は企業にどう見られているのでしょうか。
企業から見たシニア社員への期待の状況としては、「専門性の発揮」「取引先や人脈の伝承」「後進の育成」が「期待に応えている」項目として上位にあがっています。
ただし、それらも「期待に応えている」と企業が感じている割合はいずれも30%程度となっており、シニア社員の仕事のパフォーマンスとしては課題が残る結果です。
◆企業のシニア社員への課題感
さらに、企業のシニア社員への課題感を見てみると、「モチベーションの低さ」、「パフォーマンスの低さ」、「マネジメントの困難さ」が上位にあります。
いずれも「すでに課題となっている」割合が40%以上という厳しい結果です。
◆シニア社員が活性化しない影響
シニア社員のモチベーションやパフォーマンスの低さといった不活性は、周囲の若手社員にも影響を及ぼします。
普段の仕事のパフォーマンスの低下はもちろん、他社への転職率も高くなることがあるため、企業としては注意が必要です。
逆に言えば、シニア社員がモチベーションを高く持って仕事に取り組み、後輩の指導などに意欲的に取り組む企業なら、シニア社員自身だけではなく会社全体に良い影響を与える効果があるということになります。
若手社員の転職以降の抑制にもつながるでしょう。
シニア社員の人材育成の課題

シニア社員は、うまく活性化すれば会社全体にも良い影響を与える人材ですが、逆に活性化や人材育成に課題を抱える企業も多いでしょう。
ここではシニア社員の人材育成の課題について見ていきましょう。
◆マネジメントが難しく人材育成できない
シニア社員のマネジメントが難しいという点は、大きな課題のひとつです。
定年などを機にシニア社員に役職を退き、それまで部下だった年下の社員がマネジメントをすることになると、年下の上司が気を使い過ぎる傾向があります。
シニア社員も立場が変わったことを自覚できず、以前と同じように周囲に振る舞ってしまうこともあるかもしれません。
そうなると若手社員はシニア社員への対応がしにくくなり、気まずくなったりギクシャクしたり、組織の雰囲気が業務に影響を与えることもあるでしょう。
シニア社員には一歩引いたところから若手社員をサポートする立ち位置をしっかり理解してもらう必要があります。
◆モチベーションが低い
シニア社員の中には、定年や役職定年などキャリアダウンをきっかけに仕事への意欲を失い、モチベーションが低下する人もいるかもしれません。
それまでは現役でプロジェクトや人材をけん引していた社員が、年齢を境に役職や責任ある仕事から外されることは、やはりショックが大きいのではないでしょうか。
またキャリアダウンに伴う収入の低下も原因のひとつです。
役職や収入が減ったのに業務内容が同じであれば、さらにモチベーションの低下につながるかもしれません。
企業としては、シニア社員が仕事への意欲を高く保ってもらえるようにする動機づけを検討する必要があります。
◆業務設定や部門配置の難しさ
何十年というキャリアを築いてきたシニア社員は、それぞれ保有するスキルは異なります。
職種の違いもありますが、同期入社の社員同士でも個々の能力やパフォーマンスのレベルには差が出てしまうものです。
そのため任せる業務内容や部門の配置の難しさという課題もあるでしょう。
また、シニア社員の年代を考えると健康への配慮も必要になります。
もちろん一人ひとりの体力や体質も異なるため、一概には言えませんが、体に無理のないように働いてもらえる業務内容や仕事量を見極めることも重要です。
◆待遇や評価の難しさ
前述の通り、シニア社員は個々の能力や適性が異なります。
「シニア社員」とひとくくりにして賃金体系を一律にしたり評価制度が不透明だったりすると、不満の声が寄せられてしまう可能性もあるでしょう。
一定の基準は必要ですが、他の社員同様に一人ひとりのスキルや成果をしっかり評価し、成果に合わせた待遇を検討することも必要です。
給与体系の基準やパフォーマンスの違いをどう報酬に反映するかも、大きな課題と言えます。
それまで会社をけん引し、貢献してくれたシニア社員へのリスペクトは大切ですが、だからといっていつまでも同じ待遇を提供するのは無理が出てしまうでしょう。
時には厳しく、はっきりと会社としての意向を伝えることも必要になります。
シニア社員を活性化する人材育成には何が必要か

ここでは、貴重な戦力となり得るシニア社員の活性化に企業にとって何が重要かを見ていきましょう。
◆変化適応力が活性化の鍵になっている
シニア社員の活性化には、まず「変化適応力(トランジション・レディネス)」に着目するべきです。
変化適応力の高さは、仕事のパフォーマンスはもちろん、状況に応じた業務内容の変更に対して意欲的に仕事に取り組む姿勢にもつながります。
また、積極的に新しい仕事を覚えたり学習したり、自己研鑽を続けることもできるでしょう。
状況の変化に伴い、他社の方が自分のスキルを発揮できると思った場合は、転職活動をしても採用される可能性が高いと言えます。
◆変化適応力と社内活躍見込み
変化適応力に対して、今後も社内で活躍できるという「社内活躍見込み」を比較してみると、組織への帰属意識は高いと言えるでしょう。
ただし個人のパフォーマンスでは変化適応力の方が高く、仕事へのパフォーマンスにも大きく影響します。
年齢を重ねるほどその傾向は強くなり、社内活躍見込みの影響は弱まっていく傾向にあります。
どの年代の社員にも高いパフォーマンスを発揮してもらうためには、自社だけではなく、他社でも通用する変化適応力を身につけてもらう必要があると言えるでしょう。
◆人材マッチング機能でシニア人材を育成
変化適応力の高いシニア社員が活躍する企業の特徴として、社内の人材マッチング機能の強化があげられるでしょう。
社内公募や希望する部署に自分を売り込む「社内FA制度」や「社内副業」といったジョブマッチング制度が充実している企業は、社員の変化適応力が高い傾向にあります。
また、社員の希望が反映された異動や転勤も多く行われる環境が整っているでしょう。
部署ごとに、どんな職務や役職が必要とされているか、そのポジションにつくためにどんなスキルが必要かなどを社員に明示し、社員の中長期的なキャリア形成を促すことも期待できます。
40代50代におすすめの転職サービス
40代50代におすすめの転職サービスを紹介します。
サービスによって求人の内容が異なりますので、様々な転職サービスに登録することをおすすめします。
良い求人が見つからなかった、紹介されなかった場合はすぐに退会しても問題ありません。
| 転職サービス | こんな方に おすすめ | 特徴 |
|---|---|---|
|
レバテックキャリア |
40代のITエンジニア経験者 |
|

リクルートエージェント |
転職を考えているすべての方、正社員希望の方 |
|
|
リッチマン介護 |
介護職を希望の方 |
|
シニア社員を人材育成して得られるメリット

シニア社員を活性化させることで、企業が得られるメリットはどんなものがあるのかを見ていきましょう。
◆人脈や経験を活用できる
シニア社員は、これまで長年にわたって会社を発展させてきた功労者とも言える存在です。
その豊富な経験やノウハウを活かしてこれからも働いてもらったり、後進を育てたり、社内での活躍も期待できます。
仕事関係で培った広い人脈も、若手社員にはない貴重なリソースです。
有効活用できれば大きなメリットとなるでしょう。
◆採用コストや教育コストが抑えられる
新卒や中途採用など、新しい人材を採用する場合は、求人サイトなどへ掲載する際の広告費や会社説明会の準備、面接に携わる人員など、多くのコストがかかります。
入社後も、業務の進め方や会社の経営方針など、基本的なところから教育していく必要があり、育成コストも必要です。
しかし社会人としての基本的な知識やマナーはもちろん、専門知識やスキルを持つシニア社員が人材教育を担うことで育成コストを抑えることができます。
スキルを活かす場ができることで、シニア社員のモチベーションを保つこともできるでしょう。
◆他の社員や若手に安心感を与える
シニア社員が生き生きと活躍している職場なら、「ここなら長く働けそう」という印象を持ってもらいやすいため、若手社員の転職抑止にもつながります。
結果的に社員の定着率も高くなり、組織としての体制も安定するでしょう。
シニア社員の活躍を促すことは、他の社員への安心感にもつながり、組織がうまく機能することも期待できます。
まとめ

シニア社員は、今や企業にとって必要不可欠な人材です。
シニア社員を活性化させることができれば、若手社員への良い影響が期待でき、会社全体の安定や利益にもつながる可能性があります。
今回の記事を参考にして、シニア社員に活躍してもらえる環境を整えてください。
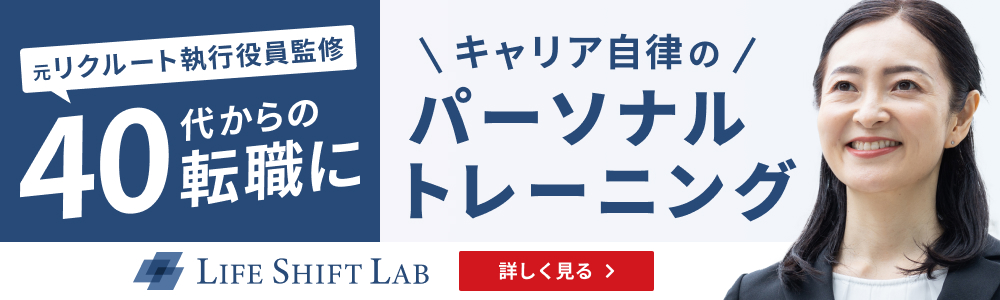
40代・50代のミドルシニア転職求人に関連するキーワードで掲載求人を探す
40代・50代 東京 営業 |40代・50代 大阪 営業 |40代・50代 東京 事務 |40代・50代 東京 飲食 |40代・50代 東京 エンジニア |40代・50代 神奈川 エンジニア |40代・50代 東京 経理 |40代・50代 東京 施工管理 |40代・50代 大阪 飲食 |40代・50代 大阪 エンジニア